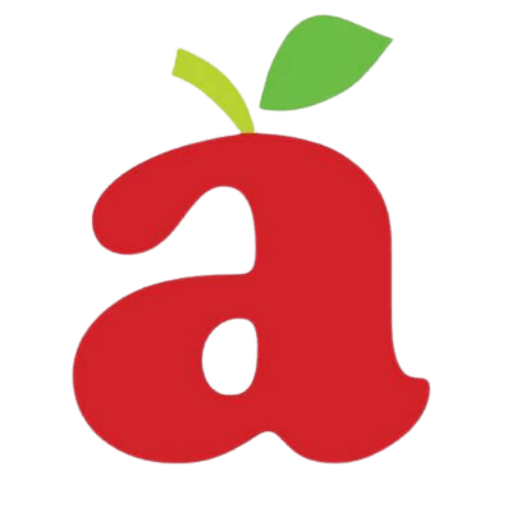
こんにちは。英語教材編集者×プロ家庭教師のあんです。
2021年1月、センター試験が廃止されて初となる「大学入学共通テスト」が実施されました。
編集という業務上、リスニング・リーディングとも分析してみました。というか、プロレベルで徹底的に傾向と対策を考え抜きました。
また、家庭教師もやっていますので、大学受験生に共通テストの指導もしています。
リーディングの対策は、実はとてもシンプルです。以下で詳しく解説します。
リーディングの傾向
概要
試験時間・配点
試験時間80分/配点100点(ちなみに、リスニングも同じく100点なので、「読めればいい」といった時代は終わったと言えるでしょう。)
全体概観
身近なものをテーマに、ディベートやプレゼンの準備を想定した出題をするなど、「実際的・実用的」な設定も目立ちます。また、「思考力・判断力・表現力」を測るべく複数の情報を照らし合わせる問題も増え、正解が1つだけでない問題も含まれています。これらは新しい学習指導要領を反映した内容と言えるでしょう。
引用:日本速脳速読協会
センター試験との違い
総単語数が約4200語→約5400語にアップ
引用:日本速脳速読協会
発音、文法、語法問題がなく、すべて長文読解に
設問がすべて英語
日本語注釈が存在しない
答えが1つとは限らない問題が出題
設問別分析
設問ごとの分析をちゃんしようと思うと、リスニングと同じようにしっかり分析することも可能です。


実際に深く分析しました。編集者としての業務上。
でもあえて言わせてください!!
あんまり深い話できない・・・。
だって傾向全部同じだから。
難易度はめちゃめちゃは高くない。
ただ読む量がめちゃめちゃ多い。
以上。
大手予備校や有名講師の方も昨年の共通テストの分析を結果を出していますが、わたし個人としては、キムタツ先生の分析にわりと共感しています。


じゃあどうやったら量が多い英文を読んで、得点できるようになるのか?
次で対策を紹介していきます。
リーディングの対策
前述の通り、共通テストは、読解力の問題というよりも、多くの情報を短時間で処理する”処理能力”の問題になってきます。速く読んで、必要な情報を探すことがが大事。得点できるかどうかは、その一点にかかっています。
速く読むためには、日ごろから速く読むトレーニングをしておくほか、スキミングやスキャニングの技術を知っておくといいでしょう。
単語力・文法力があることを前提とした上でのトレーニングやテクニックの解説です。
トレーニング
いきなり速く読めっていわれたからって速く読めるものではありません。
「練習は本番のように、本番は練習のように」といわれるように、日ごろから速く読むトレーニングをしておくことは本当に大事です。
トレーニング方法は、詳しくは次の記事で紹介しているので、速く読むコツがつかめないというひとは、1回だけでいいから目を通して試してみてください。方法を知っているか知らないかで全然違ってくるから。
ただ、次の記事ではテクニックのようなものは解説していません。ふだんから速く読むようには心がけているけど、もっとテクニック的なものが知りたいという場合には、これをスキップして次の解説を読んでみてださい。


テクニック
スキミング
skimには「液体などの表面から何かをすくい取る」という意味があるんですが、ここから派生した言葉がスキミングで、拾い読み・流し読みをする技術のことを指します。
文章全体を流し読みしながら、その文章が主に何を言いたいのかをざっくりつかんでいきます。
文章の出だしで重要な用件が伝えられていたり、各段落の一文目にその段落の要点がまとめらていることが多いので、はじめをちょっと丁寧に読んで、あとはさらさら目を通していくのがいいでしょう。
共通テストの場合は、ほんとにさらっと全体の雰囲気をつかめるだけで、だいぶ得点できる気がします。
丁寧に読む:文章の出だし、各段落の一文目
さらっと読む:そのほかのところ



様々な文章を読みこなしておく経験も、スキミングに役立ちます。過去に読んだことあるのと似た内容だったり、知ってる分野の話題だったりすると、文章って読みやすいですよね?
スキャニング
英語のscanには「ざっと見る」という意味がありますが、リーディングの際のスキャニングも同じで、キーワードになりそうな語句や関連がありそうな部分をざっと見で探す技術です。
必要な情報だけを探せばいいので、逆にいうと、全部は読まない技術ともいえます。
これは個人的な見解ですが、大問2のB以降ではおすすめしません。大問2のB以降はやっぱりちゃんと文章を読んだほうが、なんだかんだで速く正解を探せると思うので、さらさら読みをするスキミングをおすすめします。
では、どこでスキャニングの技術を使うかというと、大問1のポスターやチラシ、大問2のの料理のレシピ+レビューみたいな、視覚的に情報がとらえられる問題を解くときに、この手段がとっても有効です。
ポスターやチラシ、インターネットのレビューなどは、全部読まなくてもいい。



いろいろ書かれている中でも関係がありそうな部分をいかに早く探すが勝負になってきます。英語力そのものよりも、英語で書かれた資料を見慣れていて、どのへんに目を付けたらいいのか知っているということが大事です。
全部読む vs 全部読まない
この記事を「共通テスト 英語 全部読まない」「共通テスト リーディング 全部読む」のように検索してきてくれてる受験生が増えてきました。
そんな受験生に、家庭教師としての意見を伝えると、これ人によるから、模試や自習で自分でどっちが向いてるか試してみて!
英語が得意な受験生なら全部読み切る時間はあります。だったら変に読み飛ばすよりはさらさら読むスキミングを取り入れながら全部読んだほうが、重要な情報を見落とす確率が低くなるから安心ですよね。
英語が苦手で時間が足りない受験生なら、全部読む時間はなくなっちゃうはずだから、無理やり全部読まなくてもいいと思います。
選択肢は先に目を通す vs 目を通さない
これも人によります。(なんかこんな回答ばっかりでごめんね。でも本当にそうなんです。)
先に問題や選択肢に目を通しておいたほうが、本文から答えの根拠を探しやすい受験生もいれば、問題や選択肢に先に目を通しておいてもあまり頭に入らないから、最初から本文を読んだほうがいいと受験生もいます。
これどっちも正解はないんですよね。だって、自分の正答率が高くなる方法こそが正義っていうことだから。
だから、これも模試や自習を通して、どっちが自分に向いているのか試してみましょう。
まとめ
共通テストのリーディング対策として、特別にすべき勉強はありません。
日頃から単語や文法をしっかり勉強して基礎を固めておくこと。そのうえで、文章を速く読む意識をもってトレーニングをしておくこと。
目が通せれば解ける!!がんばりましょう。
共通テストのリーディング対策
- 内容は深くない。
- 短時間で速く処理することがすべて。
大学受験に必要な知識や情報をこちらにまとめています。
関連記事


