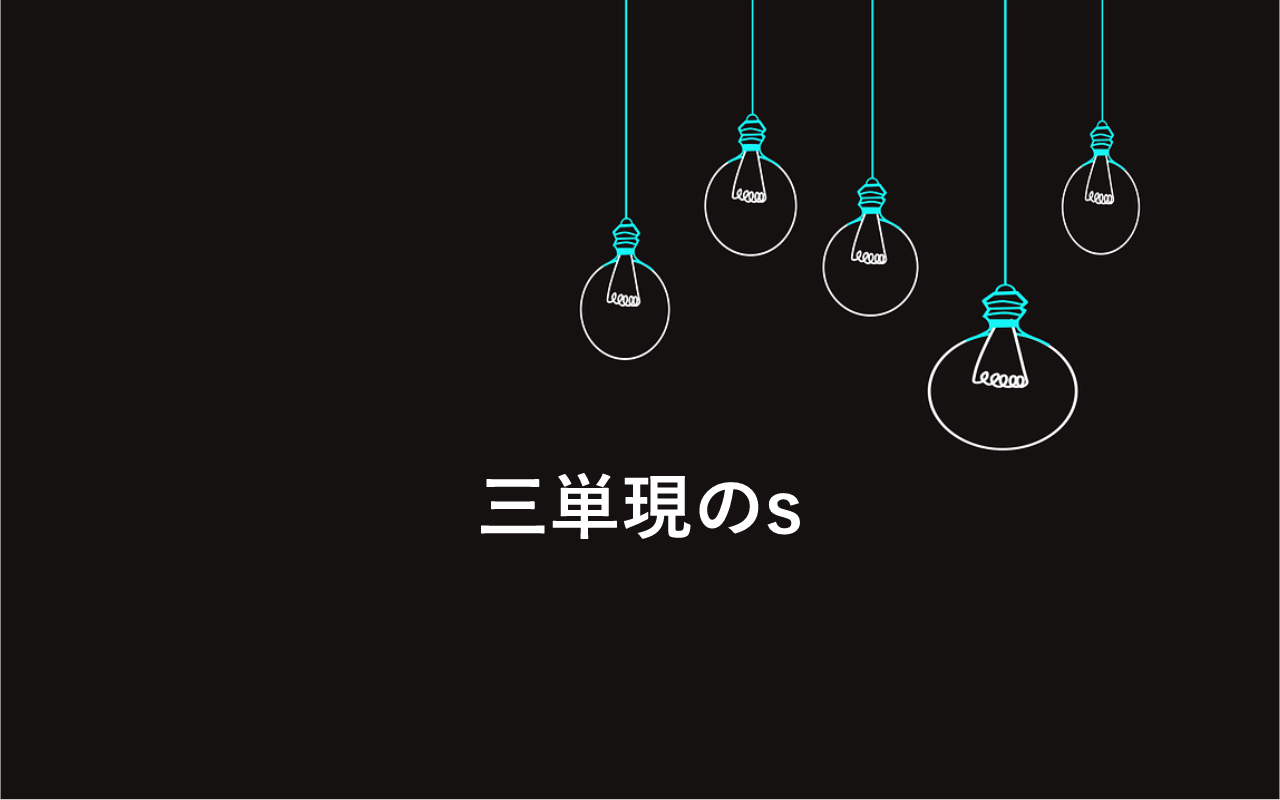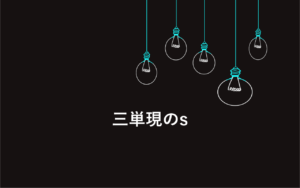英語を学び始めてしばらくすると、急に動詞にsをつけないといけないパターンがでてきますよね?
しかも「サンタンゲンノエス」とかいう宇宙人みたいな言葉が出てきて、だいたい「え、なんで急に!?今までつけなくてよかったじゃん。理由は!?意味わかんねー。ていうかサンタンゲンってなんだよ。めんどくせー」ってなって英語が苦手になります。(元塾講師のわたし談)
どんなときになぜsをつけないといけないのでしょうか。
sをつけるとき
sをつけないといけないのは、他人の話、またはなにかのモノをしているときです。
「今はわたしでもあなたでもない他人(なにかのモノ)の話をしてますよー」という合図としてsがつきます。
He likes this book.
彼はこの本が好きです。
みたいなとき。
ただ、ひとつ気をつけないといけないのは、sがつくのは、他人が1人のとき、またはモノが1つでないといけないんですね。
They likes this book.
彼らはこの本が好きです。
のように、他の人やモノが複数のときは、sはつきません。
わたしでもあなたでもないひとりの人(ひとつのモノ)のときにsがつきます。
sをつける理由
ではなぜ、他の人や他のモノの話をするときにsがつくというと、どうも英語という言語の歴史と関係があるようです。
英語は次の表のように変遷してました。
| 主語 | 14世紀 | 16世紀 | 現代 |
|---|---|---|---|
| I | singe | sing | sing |
| You | singest | singest | sing |
| He / She | singeth | sings | sings |
| We | singe(n) | sing | sing |
長年のなかで英語はどんどんシンプル化されてきたんだけど、いまだに他人の話やモノの話をするときにはsが残っているということだそうです。
余談ですが、ほかの言語だとまだまだ複雑な活用が残っているものがたくさんあります。
たとえば、わたしはフランス語専攻だったんですけど、フランス語の活用は次のような感じでした。
| 主語 | 動詞 |
|---|---|
| J’(わたし) | aime |
| Tu(あなた) | aimes |
| Il / Elle(彼 / 彼女) | aime |
| Nous(わたしたちは) | aimons |
| Vous(あなたたちは) | aimez |
| Ils / Elles (彼らは / 彼女らは) | aiment |
英語って意外とシンプルなんだなということがわかります。
sをつけるときの基本的なルール
わたしでもあなたでもない他のひとりの人(ひとつのモノ)のことを語るときにsがつきます。(大切なので何回も言います。)
基本的にはそれだけ覚えておけばいいんですが、文字に書き起こすときのルールがあるので確認しておきましょう。
| 基本のルール | 語尾にsをつける。 例:come(来る)→comes |
| s, o, x, ch, shで終わる動詞 | 語尾にesをつける。 例:do(する)→does |
| <a, i, u, e, o以外の子音>+yで終わる動詞 | 語尾のyをieに変えてsをつける。 例:carry(運ぶ)→carries |
| 特別な変化 | have(もっている)→has |
まとめ
英語を勉強しだしてまずつまづくとこって動詞にsがつくとこなんですよね。
この記事を理解・克服できたあなたはどんな英文法でも吸収できるはず。
引き続き英語の勉強がんばっていきましょう。
三単現のs
- わたしでもあなたでもない他のひとりの人(ひとつのモノ)のことを語るときにsがつく
関連記事